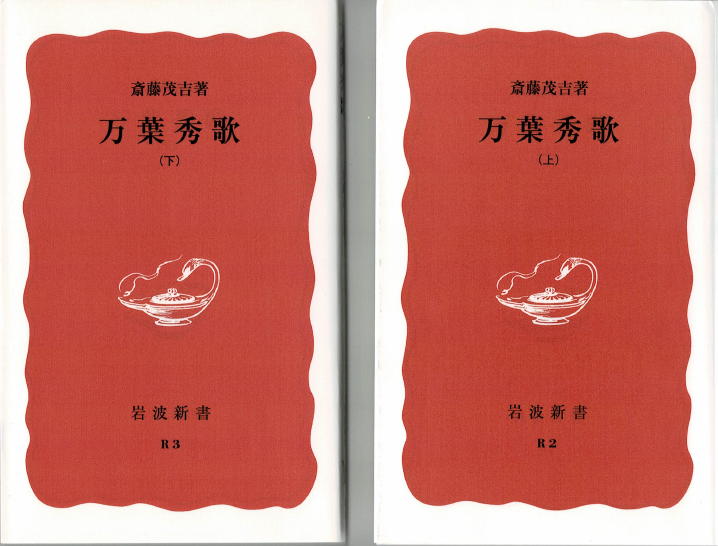ようやく風土記の補遺の続きを書くことができる。セルバンテス-シェイクスピアの時ほど態勢を整えたわけではないが、深入りすれば切りがないので準備はここまでとする(補遺と言うには長いので、別のタイトルをつけることにした)。そう決めた後、先日補遺の続きを断念することになった理由が腑に落ちた。私は「作者」について調べた上で、関連する歌や漢詩にあたればそれですむと思っていた。しかし、別の難問が水面下に隠れていて、そこで座礁したのだった。
作品の鑑賞という問題が、私には見えていなかった。好みを言うだけなら、どう読もうと勝手だろうが、私は常陸国風土記の特別な長所について述べたいのである。となると、その「作者」候補者の位置づけや 、彼らの作品がどう読まれて来たかについて、ある程度は押さえておく必要がある。遠い昔に書かれたものを読み、楽しむことで、私はこれまで概ね満足していたのだった。
しかし、補遺で解こうとした問題は、こうした無為の楽園から一歩踏み出さずには解決できないものだった。となると、高橋虫麻呂や春日蔵首老の歌が採られた万葉集の全体と取り組む必要があるのだろうか? そうすべきかもしれないが、短歌と縁が薄い私には難しい。そこで、ハムレット論に深入りする代わりにスティーヴン・グリーンブラットを案内役としたように、万葉集についてもガイドを立てて導いてもらうことにした。
斎藤茂吉『万葉秀歌』(上の写真)。昭和13年の初版以来、令和の今日に至るまで毎年のように増刷している。知ってはいても縁のない本だと思っていた。同書を初めて開き、第一首目を読んで衝撃を受けた。
たまきはる宇智の大野の馬並めて朝踏ますらむその草深野 中皇命(巻一・四) 舒明天皇に献じた歌。「今ごろは、[たまきはる](枕詞)宇智の大きい野に沢山の馬をならべて朝の御猟をしたまい、その朝草を踏み走らせあそばすでしょう……草深い野が目に見えるようでございます」
この歌を冒頭に置く茂吉の慧眼と手腕。「日本語の優秀な特色が隈なくこの一首に出ているとおもわれるほど」と。確かに。清みきっていて、力強く、宏大。素晴らしい歌を読み過ごしていた自分自身への驚きと落胆。私は万葉集にちゃんと取り組んだことはなかったが、この歌は冒頭四番目なので、一度や二度は読んでいたはずなのだ。
そう言えば西行を好きになったきっかけである「さ夜の中山」も、大学時代にたまたまTVの大学講座か何かで紹介されるのを見て、こんなすごい歌があるのかと驚いたのだけれど、小林秀雄の「西行」に引かれているのだから、以前に(それも、そんな前にではなく)読んでいたのは間違いないのである。記憶力の問題、短歌への感受性の問題……。その後、西行を少しは読んだけれど、それ以外短歌の世界にはノータッチのままだった。
茂吉は、中で参照する契沖、賀茂真淵らの21の注釈書をあげている。素人には踏み込めそうにない魔境だ。『秀歌』は、「万葉の精神」などより「一助詞」について論じる(序)という姿勢が徹底していて、時に独断的な書きぶりも公正さ装わないという意味で却って信頼が置ける。おかげで、万葉集の優れた短歌や歌人について、概要を知ることができたと思う。
万葉集への寄り道が役立つのは、もう少し後になる。その前に、常陸国風土記の「作者」が誰なのか方をつける必要がある。しかし、今回は紙数が足りない。前から作者候補者たちの名前が気になっていたので、ここにメモを残しておきたい。春日蔵首老に高橋虫麻呂、藤原宇合と癖のある名前揃いなのだ。
宇合は馬養からの改字で、現代の目には威厳に欠ける名前に感じられるが、藤原不比等の第三子であり、後の藤原氏四家中の式家の祖となるエリートである。虫麻呂(蟲麻呂)も今から見ればおかしな名前だが、虫のつく名は当時他にも例が多く、特に異とはされないようだ。
春日蔵首老となると字面からして不気味に感じられ、詩人らしくもない。春日は地名。但し奈良県ではなく大阪河内。帰化人の多い地域で、彼らは貿易に従事し、官の倉庫の管理もしたらしい。で、蔵(倉)の一字。首は「ひと」とも読み、臣や連より下位の姓。老はこうした家系の出身のようだ。7世紀末から8世紀にかけて、僧侶を還俗させて役人とする例があり、老はそうした一人だった(僧侶時代の名は弁基)。
老は、現代では名前と認識することすら難しいが、当時はよくあったものらしい。万葉集中では間人連老(先にあげた「たまきはる」の歌の実際の作者とする説がある)、穂積朝臣老、小野朝臣老ら。折口信夫は「『老』は貴族の若者に使」うと述べている。若死には普通のことで、長生きが珍しかった時代、「老い」はポジティヴな属性として名前に用いられたのだろうか?