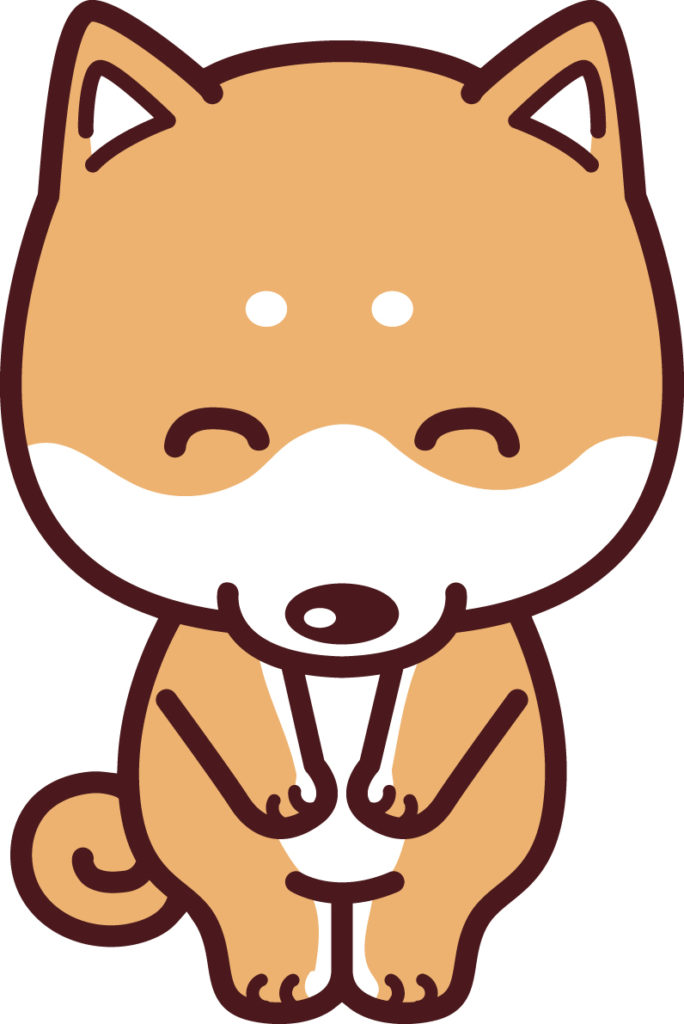
本文を一部訂正しました
コロナ禍の影響が、このブログのような片隅にまで及びました。『二重の欺瞞』について検索していたら、合作説を否定する日本の学者の論文があることが分かりました。これは『二重の欺瞞』偽作説に直結するものと思われます。中身を確かめるのに、普段なら国会図書館に行けば一日で片づくのですが、新型コロナの影響で休館中。
6月11日からは抽選で1日200人ずつ入れると開示されたものの、最初の申し込み締め切りはすでに過ぎていました。私のくじ運からすると当たるとは思えず……遠隔複写を申し込みました。これを読んでから#63を書くつもりです。今回は、#61で予告しながら後回しにしていた翻訳について語ることにします。
辞書を引き引き『青白い炎』を解読し、私の読解力が及ばないところは日本語訳を参照するので、ずーっと原文と訳文を行ったり来たりしていました。当然なかなか先に進みませんが、苦労してでも原文を読む方が楽しいと感じていました。
ナボコフの文章は凝っています。古語や学術用語が遠慮会釈なく……というか意図的に濫用され、その中に作者謹製のゼンブラ語さえ混じります。恐らくネイティヴな英語読者でも首をひねることが結構あるのではないでしょうか。しかし翻訳では、富士川義之訳(岩波文庫)でも、森慎一郎訳(作品社。こちらの題名は『淡い炎』)でも、ナボコフが繰り出す魔術の呪文のようなスタイルからは遠いあまり癖のない訳し方をしています。
短い一文を例に挙げます。’Thither trudged our thug’ 私の英語力ではどういう意味か見当もつきません。富士川訳では「そこへ殺し屋はとぼとぼと歩いて行く」、森訳では「我らが刺客はとぼとぼとそちらに歩を進めた」。両氏の訳は、恐らく正確さを旨とし(『ロリータ』の最初の日本語版は悪訳だったとか)、英語が母国語ではない外国人であるナボコフが、ペダンティックなゼンブラ国出身者(を騙るロシア人学者?)を騙って書いたという設定の中で、翻訳が難しい「文体」については見切ったのだと推察します。
かつてジョイスやバースなどの翻訳で、訳者が技というか芸というか、競っていた時代があったように記憶しています。冷静に考えれば、いくら訳文に凝ったところで原文に近づけるわけではありません。しかし、「人工的」であれ、原作の香気が些かでも味わえるなら、そういった訳にも価値があるような気はします。残念といえば残念。
原文の方が楽しいと感じるのは、根本的にはより作者に近いところで作品を読めるからです。ならば、ネットの恩恵で「原書」の入手が簡単になった今、原文で読む価値があると感じられるほどの作品は、「本物」でその香気を味わうべきということになるでしょうか。香りはなくとも正確な翻訳を片手に。私の場合、英語以外ではそうした手を使えないので、海外文学の良い翻訳がこの先も途絶えないことを祈ります。
さて、厳しい『青白い炎』修行と電子辞書のおかげで、前回文献としてあげた2冊をさほど苦労せずに読むことができました。しかし、こうした研究系の本については翻訳で読んでも殆ど問題がありません。必要な情報を摂取するのが目的であり、香りは普通は必要ないからです。それどころか、私の貧しい英語力による誤読が避けられるという大きなメリットがあります。というわけで、英語で読むのが楽な本はあえて英語で読む必要がなく、英語で苦労する本こそ英語で読むことで得られるものが多いという葛藤が生じます。
以下、以前の投稿にあった文章をカットしています。確認すればいいだけのことなのに、思い込みで誤ったことを書いていました(ロジェ・シャルチエの文章云々です)。お詫びします。トップの画像も、お詫び画像に変更しました。また、その他の部分にも訂正をした箇所が少しですがあります。(2020年7月10日)
