
バビロンの車市場にて
バビロニアによる捕囚とアケメネス朝ペルシアの支配の下でも、ユダヤ人は一つの民族集団として生き抜くことができた。独自の国を再建することはかなわず(第二次世界大戦後のイスラエル建国まで)、各地に分散して居住(ディアスポラ)しながらも、「宗教民族」として存在し続けたのである。その核に、ヤハウェ以外の神を認めない一神教という宗教の独自性があった。
しかし、先祖伝来の土地と結びついた民族的な基盤を根こそぎにされる捕囚のような状況では、独自の信仰や生活習慣が失われていくのは自然な成り行きだ(現代でも、同胞コミュニティのない国への移民なら同じこと)。バビロンに閉じ込められたユダ王国の人々は、そのような有様を周囲で見聞きし、また我が身のこととして体験していたはずだ。その結果どうなるか、彼らは捕囚以前に知っていたのである。
ヤハウェ信仰を共にするイスラエル北王国の人々は、アッシリアによって各地に分散して居住させられ、民族としては雲散霧消してしまう(いわゆる「失われた十部族」)。南のユダ王国には北王国の滅亡から逃れて移住した人も多く、彼らは山我哲雄氏の言う信仰上の「革命」の担い手ともなった。北王国の滅亡を直接、間接に知る人々は、捕囚という状況下、北王国の悲劇を繰り返さず、民族を存続させるために何が必要か懸命に考えたはずだ。 続きを読む



 バビロンにて(六本木ヒルズではない、はず)
バビロンにて(六本木ヒルズではない、はず)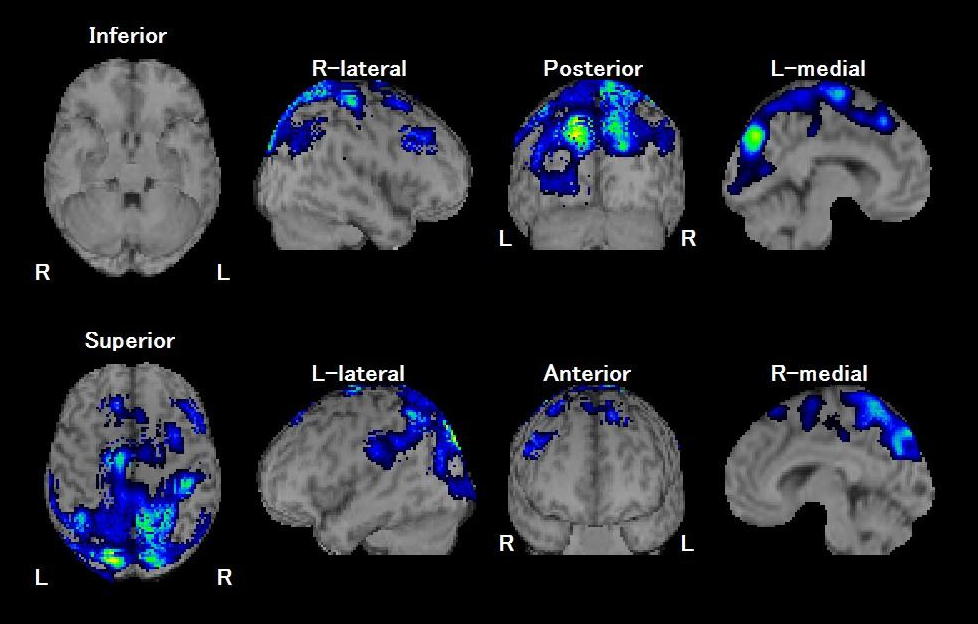 やばい自画像。
やばい自画像。 バビロンへ続く道(渋谷だったかも?)
バビロンへ続く道(渋谷だったかも?)