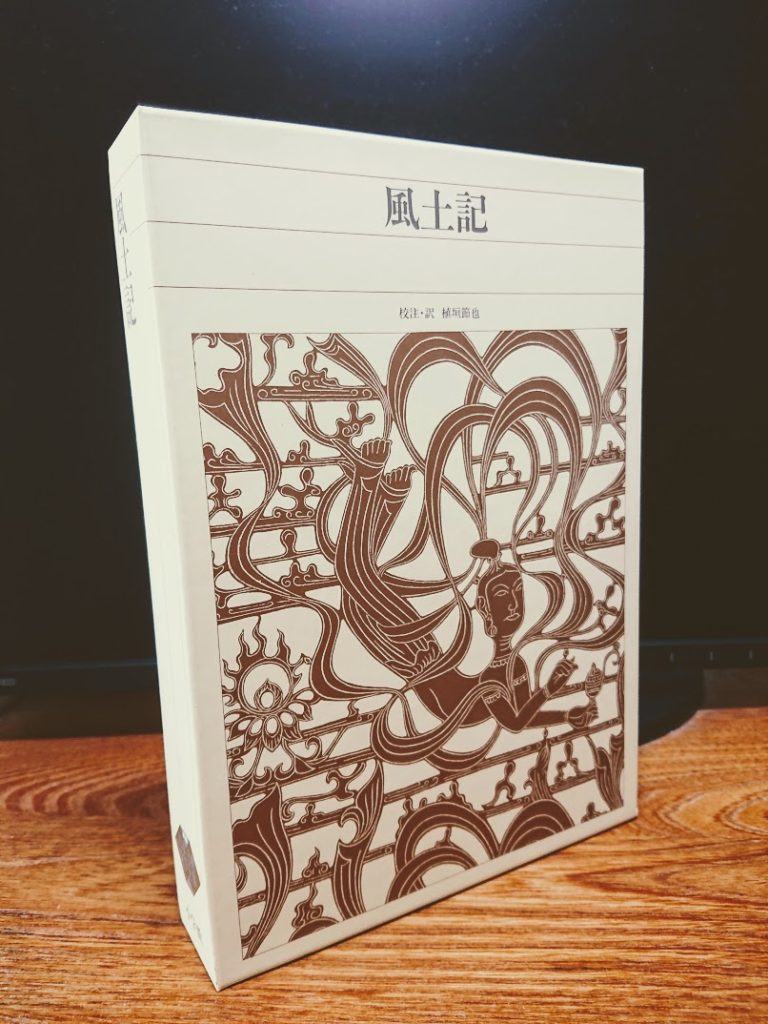
民衆の姿を描いた万葉歌人と言えば、一も二もなく山上憶良だろう。そもそも無名の防人や相聞の主観による歌を除けば、憶良の作以外、万葉集の中で庶民が描かれることは少ない(高橋虫麻呂は例外の一人)。彼の代表作「貧窮問答歌」に漢文学の影響がみられることは、国語の教材として教えられることは滅多にないものの、研究者にはよく知られており、実は斎藤茂吉『万葉秀歌』(#74)にも指摘がある。
万葉集自体、漢文学の影響が大きい。国文学者の小島憲之氏は、万葉集を代表する歌人柿本人麻呂は「ほかの歌人にくらべてより多く漢籍をひもといた事は疑がない」とし、憶良は「漢詩文が自らこなせた事は萬葉人の中でも上位にある」と記している。憶良が冠位のないまま遣唐使の少録(記録係補佐)に選ばれたのは抜群の「語学力」の故だっただろうし、二年間彼の地に滞在してさらに磨きがかかったはずだ。渡唐時に42歳。筑前守として九州に赴き、太宰帥大伴旅人らと交わって万葉集に収められる歌の大部分を作ったのは六十代半ば以降のことである。
春日蔵首老は、万葉歌人としては憶良と比べられないが、漢学の素養が官界での栄達を導いたのは相似だ。前回述べた通り老は新羅留学の可能性があり、中年になって政府の官吏に取り立てられて従五位下の貴族に列した。それが憶良と同じ和銅六年(714年)正月だったのは偶然の一致なのかどうか……栄達にあずかるまでの経歴が殆ど知られていないのも共通で、両者とも貴族の周辺にありつつも画然と区別される家系の出身だったようだ。そんな二人が、当時としては例外的に民衆の姿を文章にしたのだった。
憶良の直接的な表現に比して、常陸国風土記の文中、民衆の姿が目立つわけではないが、当時他に極めて例が少ないものだったことは同様だ。個人的な歌としてでなく、公的な記録の中に民衆を書きとめたことにも留意したい。私は先走って老が常陸国風土記の書き手(の一人)と決めつけているわけだが、民衆が描かれていることもその有力な証拠と考えている。三人の国司は元から貴族であり、「解」に民衆の姿を描こうとは考えもしなかっただろう(虫麻呂については、別途考える)。
二人は漢学を学ぶ際、文章で表現されるのが公文書や歴史、詩歌に限らないことを知ったはずだ。たとえば唐以前から「小説」が書かれていた。伝奇小説「遊仙窟」を持ち帰り、国内で広く読まれるきっかけを作ったのは憶良らではないか、と小島憲之氏は指摘している。貴族たちは、彼の地で学んだにしろ、輸入された漢籍を読んだにしろ、多くは文飾のためにそれらを利用(時には剽窃も)したのである。しかし、貴族でないという意味で民衆の側にいた憶良と老は、庶民が表現の題材となっていることに驚いたはずだ。二人は、文章は公的なものであり、神々や高貴な者のために書かれるものという当時は当たり前の先入観を持っていたのに、それを漢籍を学ぶことで覆されたのだから。
一方、「解」のためにレポートを作成した地方の下級役人たちは、漢文で文章を作る術を知ってはいても、憶良と老のようには漢文学の知識を持たない。歌はともかく、文章で自分たち自身の生活を書き表すことができるなどと思いつきさえしなかっただろう。文章は公的で、神々や高貴な人々のためのものという先入観の外に出ることは(漢籍に詳しい老や憶良とは違って)不可能だったのである。だから、各所の神話や伝説において、話の素材は土着の民であっても、書きとめられる時には神々や天皇、皇子、高貴な祖先の話に置き換えられてしまう。そうすることで自分たちの来歴を美化したいという動機も働いただろう。
貴族たちは、伝奇小説を含む漢籍に民衆が登場しても気にも留めなかった。まして彼らを文章で表現したいなどと考えるはずもなかった。上記の下級官吏とは逆方向からだが、貴族もまた民衆を描くことはしそうにないのである。庶民と貴族をまたいで生き、最終的に貴族の側に居場所を得た憶良と老は、漢文学の素養を活かして直接的に民衆を描いたのだった。彼らは民衆が表現の素材になり得ることを漢籍を通して理解していたのである。
さて、私は常陸国風土記の「作者」として老を名指ししたいわけだが、虫麻呂という人物が障害として残っている。虫麻呂の生涯については憶良や老以上に不明点が多いのであるが、貴族の家系の出であることは確かなようだ。その彼が民衆の姿を長歌に残している。となると、虫麻呂が常陸国風土記の書き手である可能性を容易には消去できない。それどころか、彼を「作者」とするなら、老を書き手として考えに入れる必要がなくなる。
常陸国風土記には二つの文体が混淆しているが(#77など)、虫麻呂が領国内各所からの報告をまとめ、上司の藤原宇合が#76の②のような文飾をしたとすれば、答え合わせはすんでしまう。老はなお書き手として可能性は残るものの、下級官吏の報告者と同様の立場に追い込まれ(?)かねないのだ。しかし、私には#75で示した三つの文章が、虫麻呂の手になるもの、あるいは老の手が入らないものとは認めがたい。それらは私見では虫麻呂の文体ではないからだ。老はそうした文章を書く力を持っていた。万葉集の歌を検討することで、この問題を考えてみたい。次回に続く。
