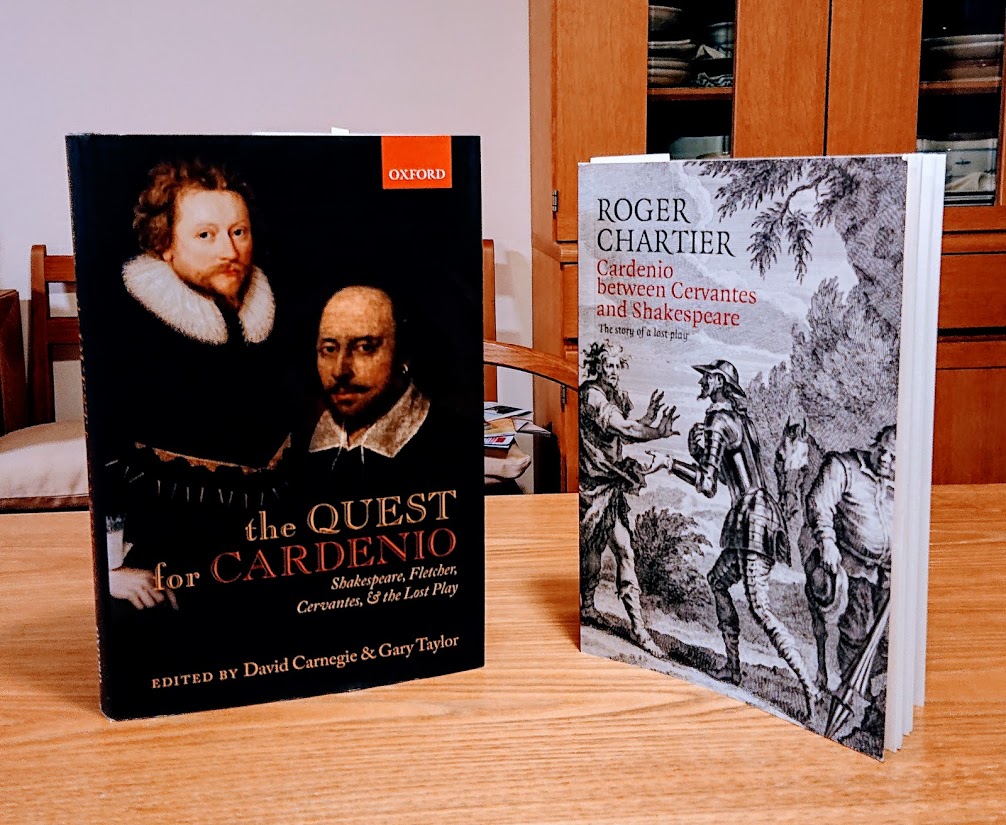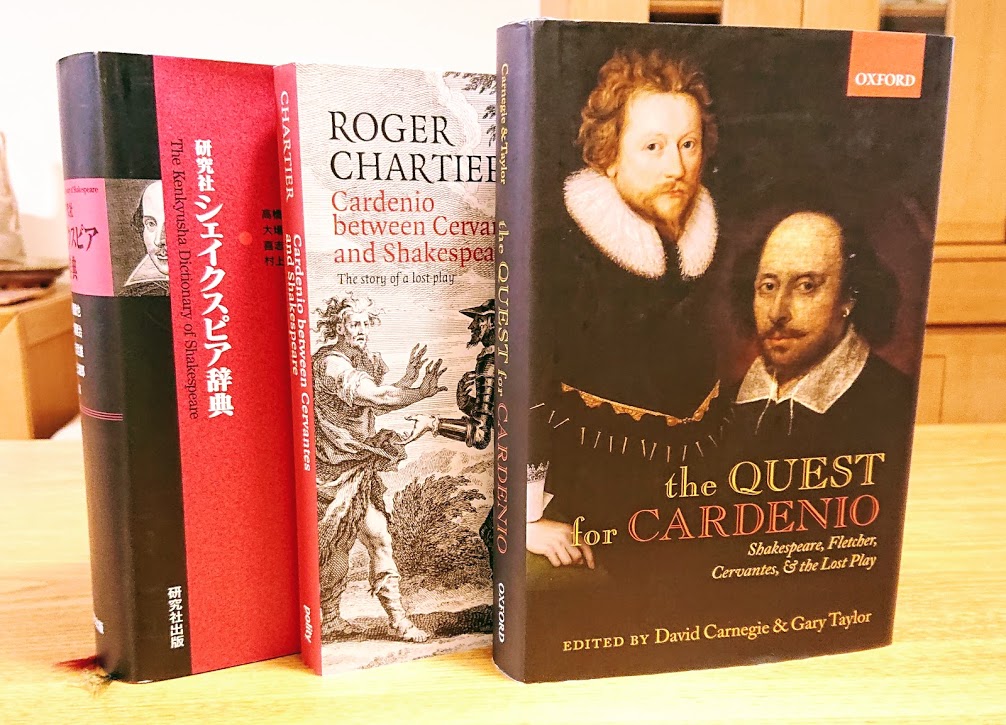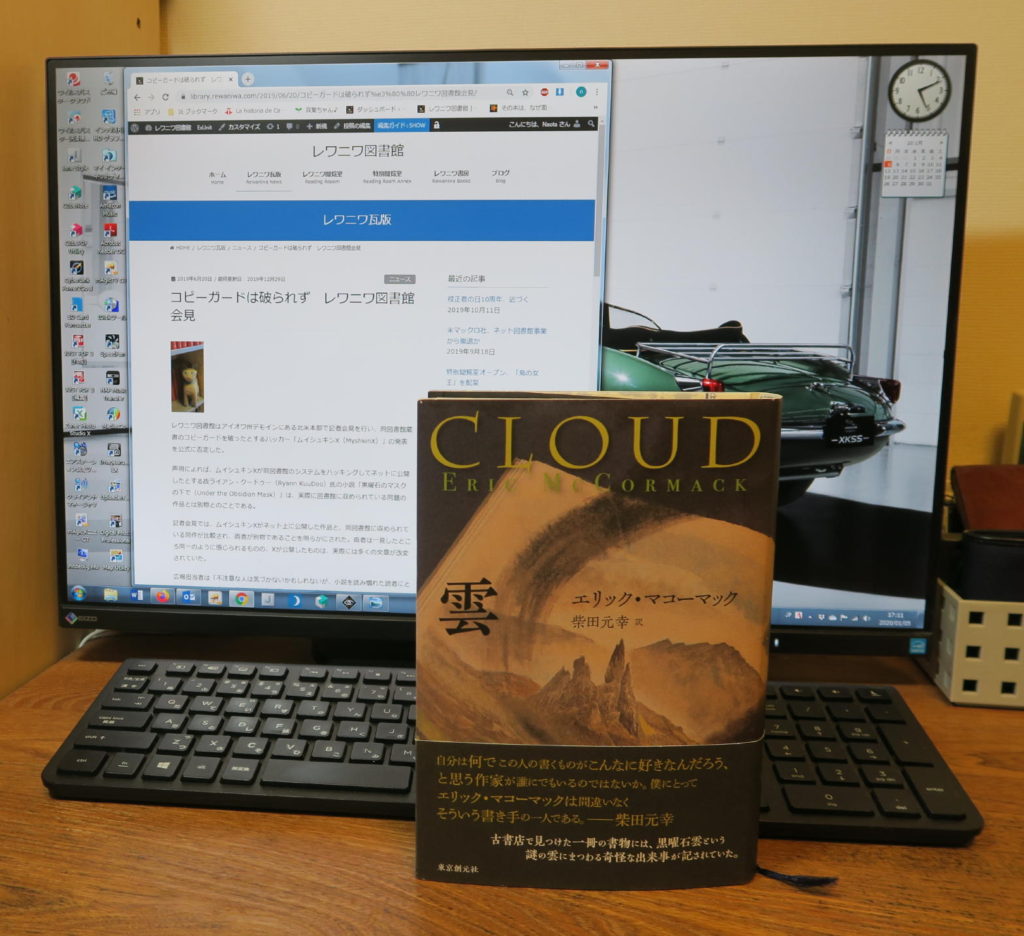#40で、「アナバシス」中に突如登場して兵たちと共にときの声をあげる「娼婦」とは何者なのか、その正体の解明に一歩近づいた。駐日ギリシャ大使館に問い合わせたところ、松平千秋氏が「娼婦」と訳した単語”etairai”(アルファベットで表記するとこうなるようだ)の意味を教えてくれたのである。”etairai”の男性形”etairos”は同志、親友を、その女性形”etaira”は高級娼婦を意味する。つまり、英語訳の註comrade-womenは同志という意味をくみ、風間喜代三氏が「芸者」と訳したのは”etaira”から来ていたようだ。ギリシャ大使館の方の示唆によれば、古代から19世紀まで、軍隊には”camp followers”がつきもので、その中に娼婦も含まれていた。
私は”camp follower”という言葉を知らなかったが、手元の電子版ランダムハウス英和辞典にちゃんと載っていた。「非戦闘従軍者:軍隊を追って移動したり、兵営の近くに住みつく肉体労働者、行商人、売春婦など」。このような「軍隊に追従し宿営地近くで商売をする人々」について、私に限らず、多くの人の視野に入っていないのではないか。戦争を商売の種と考え、軍隊と共に戦場の近くを移動する業者がいたのである。危険を伴うが、彼らはこのリスクに大きな見返りがあることを知っていたのだ。
軍隊といえばまず戦闘部隊のことを考える。その後方に、物資の輸送や補充、医療などを行う部隊が追随することは、まあ分かる。しかし、戦場を移動する戦闘部隊の後方には、軍隊に属さない「キャンプ・フォロワー」もいたわけである。古代の軍隊は街が移動しているようなものだったと言われることがあるが、キャンプ・フォロワーを含めて考えると、その様態が理解しやすくなる。そうした存在は表だって語られることが殆どなく、戦争における影の部分だった。いや、今でもそうだろう。その影にこそ、「戦場の女性」たちは存在した。彼女らは必要とされていたのである。彼女らがいなかった場合に何が起こるかを示唆する事例が、ヘロドトス「歴史」に記されている。
アテナイからカリア(現在のトルコ西南部)に来た男性たちは「移住の際女を連れてゆかなかったので、彼らの手によって両親を失ったカリアの女を妻としたのだった。この殺戮のためにこれらの女たちは、決して夫と食事を共にせず、夫の名を呼ばぬという掟を自分たちで作って……娘にも伝えたのである。現在の夫が自分たちの父や子供を殺し、そうしておきながら自分たちを妻にしたという恨みからである。」ここでいう「移住」が平和的なものでなかったのは言うまでもない。この「移住者」たちは、アテナイという出自をもって「最も高貴な血統」と誇っていたのだそうだ。
ここで突然ながら「ドン・キホーテ」に戻りたい。前に書きそびれた中に翻訳をめぐる問題があり、それは旅する娼婦をめぐるものだったのである。前編第三章、まだ一人で行動していたキホーテが、城と思い込んで訪れた宿の戸口にいた二人の女性である。二人は「馬方たち」と行動を共にする予定なのだが、兵隊たちが通りかかれば軍隊付きの娼婦にもなるに違いない。さて、その宿の主人は頭がおかしいと察したキホーテをやりすごそうと、妄言につきあってインチキな騎士叙任式を城主として行い、その際、娼婦二人をお付きに仕立てた。彼女らが見事にその役割を果たすと、キホーテは二人の「淑女」に名前をたずねる。これに対する一人の返答を、岩根國彦氏は次のように訳している。
「女はいとも淑やかに、サンチョ・ビエナーリャの裏長屋に住まい致しますトレド生まれの靴直し職の娘トロサでございます。いずこにありましょうともあなた様を主と思ってお仕え申します、と応えた。」
娼婦の中でも下級と覚しい二人を、キホーテが姫君か貴婦人と思い込んでいるのに対して、当意即妙、上流婦人風の言葉で、しかし卑しい出自は隠さず返したのが面白くて、笑ってしまった。しかし、間もなく、上流社会と無縁のはずの彼女らに、そんな言葉遣いができたのか気になり始めた。それに他の訳で前に読んだ時、ここで笑った覚えはない。で、牛島信明訳を見直してみると、次のようになっていた。
「彼女はひどくへりくだった調子で、自分は名をトローサと呼び、トレードのサンチョ・ビエナーヤ広場の商店街で働く靴直し職人の娘だが、これから先は、どこにいようともあなたを主君と思いなして、お仕えするつもりだと答えた。」
上流婦人風の言葉遣いではなかった。荻内勝之訳でも同様で、英語訳、読めないながらスペイン語版に目を通しても、女が特に上品に喋っているようには受け取れなかった。岩根氏は喜劇的効果を高めるために、あえてこのように訳したのだろうか? その効果は、少なくとも私にはあったわけだ。「超訳」とまでは言えないとしても、その方向に一歩近づいているようでもある。
翻訳ではないが、私も引用に当たり、ある種の効果をねらって省略をしたことがある。#41の「アナバシス」からの引用で、「戦闘部隊は山頂に達して……凄まじい叫び声をあげた。」と一部を省いている。「……」は、実は「海を見ると、」である。それまで、こんな短い省略はしたことがない。「海を見ると、」を入れると、先陣部隊が何を見て叫んだのか、まだ山の下の方にいるクセノポンらに先んじて読者が知ってしまい、劇的効果が薄れると考えたのだ。ただし、ホメロスなどを読むと、予言や予告で先の出来事を明らかにし、その後その通りに展開するという記述は実に多い。活字本が普及する以前、朗読が前提とされた時代には、こうした「ネタばれの予告編」が必要だったとも考えられる。現代と古代の読者とでは、作品内でのサスペンスの求め方が違っているようだ。